■危ない食後の中性脂肪上昇 ― 2012年03月22日
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/201203/523805.html
Nikkei Medical Online リポート・特集 2012/03/12
Nikkei Medical Online リポート・特集 2012/03/12
食事内容により大きく変動する血清中性脂肪(TG)値。総コレステロール(TC)値が正常でも、食後にTG値が上昇する人は動脈硬化性疾患のリスクが高い。
平光ハートクリニック(名古屋市南区)院長の平光伸也氏は、身近な高脂肪食であるファストフード(ハンバーガー、アップルパイ、清涼飲料水)を食べた後に、TG値がどのように変動するか、健常者を対象に血清中のTG値の変動を調査した。
その結果、小太りでメタボリックシンドロームに近い被験者の多くで、血清が白く濁り、TG値高値が6時間経過後も持続することを確認した。
本来、TG値は食後に上昇し、血管壁に存在するリパーゼなどにより加水分解を受け、速やかに代謝される。この代謝が遅くなると、食後数時間たっても血中の TG値が上昇したままとなる。TG値の代謝を阻害する要因は、インスリン抵抗性などが関与することも分かってきている。
TC値低値でもリスク高まる現在の「脂質異常症診断基準」では、TG値150mg/dL以上が高 TG血症と定義されている。測定は全て、10~12時間以上の絶食後が基準とされており、リスク評価の指標として食後のTG値は使われていなかった。
まずは食事・運動療法を
但し、日本人男女11,068人(40~69歳)を対象とした前向き調査の結果、総コレステロール低値群(男性183mg/dL以下、女性195mg/dL以下)でも、非空腹時TG値が高い男性において、冠動脈疾患の発症リスクとなることが示されている。(Iso H. et al.Am J Epidemiol, 2001;153:490-9.一部改変)
このような、食後に高TG値を示す、若しくはそのピークが遅延する状態は「食後高脂血症」と呼ばれ、動脈硬化性疾患の新たなリスク群として注目を集めているが、その診断基準がない。
TG値は、食事内容や食後経過時間によって同一個人内でも大きく変動する。「食後高TG血症」を見つける為には、何らかの負荷試験が必要となるが、標準化された負荷試験はないが、「脂肪負荷試験」の検討は進められ、標準化のメドは立っているが、TG値のピークを測定するには、8時間ほど経過を観察する必要があり、実臨床への導入が難しい状況ということで、今春改訂される日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」にも、食後高脂血症の記載はほとんど無いという。では、実臨床の現場ではどうしたら良いのか。
日本人の血清TC値は、過去40年間上昇しており、2000 年の調査では平均200mg/dLを超え、ほぼ米国人と同程度となっている。特に顕著に増えているのがTG値で、壮年期男性での上昇が目立つ。このTG値の上昇は、体格指数(BMI)の増加と相関する。
阪大循環器内科病院教授の山下静也氏によれば、内臓脂肪が減れば、TG値も並行して低下する。絶食後の検査で基準値内でも、内臓脂肪が溜まった小太りの患者に対しては、カロリー制限や有酸素運動などで、体重を減らすのが望ましく、食事に含まれる脂肪が食後のTG値上昇に寄与するので、脂肪摂取量を減らすことが有効だ。
■妊婦の食事、子どものアトピー発症に影響? 千葉大研究 ― 2012年03月06日
2月18日に東京都内で開催された「食物アレルギー研究会」で発表された千葉大の研究に依れば、妊娠中の食生活が、生まれてくる子どものアトピー性皮膚炎の発症に影響する可能性があることが判ったという。
2007~08年に千葉大付属病院などで出産した女性と、生後6カ月の子ども650組を分析したもので、2カ月以上かゆみを伴う湿疹を繰り返した114人(18%)が、アトピー性皮膚炎と診断した。
納豆を毎日食べた女性から生まれた子供は、7%しかアトピーを発症しなかったのに対し、そうでない場合は19%だった。バターを毎日食べた女性の子供は、35%がアトピーを発症、そうでない子は17%だった。魚・マーガリン・ヨーグルトでは差が出なかったというもの。子供がアトピーと診断された女性とそうでない女性の間で、アトピーの有無や母乳育児の割合などに差はなかった。
■「断食」はがんを弱体化させる、米マウス研究 ― 2012年03月01日
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2856573/8431061
AFP BB News > ライフ・カルチャー >ヘルス 2012/02/09
AFP BB News > ライフ・カルチャー >ヘルス 2012/02/09
米・南カリフォルニア大(University of Southern California)のバルター・ロンゴ(Valter Longo)教授(老人学・生物科学)らが2月8日の米医学誌「Science Translational Medicine」に発表したところに依れば、癌を患っているマウスに絶食させたところ、腫瘍が弱体化し、化学療法の効果も上がったという。
同教授らによる自己申告データでは、2010年に、乳がん、尿路がん、卵巣がんなどの患者10人を対象にした研究で、化学療法の前2日間と後1日間に絶食した場合、化学療法の副作用が少なかったという。ロンゴ氏によれば、がん細胞を打ち負かす方法は、がん細胞を狙い撃つ薬を開発することではなく、正常細胞だけが直ちに順応できる絶食などで極端な環境を作り、がん細胞を混乱させるということなのかもしれないという。
■風疹・はしか、海外型急増 「旅行・出張前に接種を」 ― 2012年02月23日
http://digital.asahi.com/articles/TKY201202070752.html
朝日新聞デジタル > 2012/02/08
朝日新聞デジタル > 2012/02/08
国立感染症研究所や地方衛生研究所が2011年に国内の患者から採取した麻疹ウイルス約120検体、風疹ウイルス約20検体の遺伝子の特徴を調べた結果、麻疹は東南アジア、欧州など海外で流行しているタイプがほぼ100%を占めた。海外タイプは3年前から急増しており、風疹も大半がタイやフィリピン、ベトナムなどで流行しているタイプの可能性が高かったというもので、専門家は「海外に行く前や、妊娠を希望する人は、男女共ににワクチン接種を」と呼びかけている。
妊娠初期の女性が風疹に感染すると、子どもに心臓病や白内障、難聴などの障害が出る危険がある。妊娠中に麻疹に感染すると、1/3が流産・死産したという報告もある。
風疹は、現在は男女共にワクチンの定期接種が求められているが、1977~94年までは女子中学生のみを対象とした集団接種だった為、30~40代の男性で風疹への抗体を持っている人は7~8割にとどまる。麻疹も定期接種の接種率は90%台で、30~40代で抗体がない人もいる。
■牛乳を飲んで脳を活性化、記憶や認識力アップの可能性 米研究 ― 2012年02月20日
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2854936/8400749
AFP BB News > ライフ・カルチャー >ヘルス 2012/02/02
AFP BB News > ライフ・カルチャー >ヘルス 2012/02/02
オランダの乳製品関連専門誌「International Dairy Journal」1月号に掲載された米メーン大学(University of Maine)による研究に依れば、より多くの乳製品を摂取した成人は、少量若しくは全く摂取しない人と比較して、記憶力や認識力のテストで著しく好成績を収めたという。又牛乳を多く摂取した成人がテストで失敗する確率は、牛乳を全く摂取しない人に比べて約1/5以下だったという。
本研究は、23歳~98歳の男女900人を対象に、視空間や言語、作業記憶などに関するテストを通じて、記憶力や認識力についての調査を行ったもので、8項目のテストで最も好成績を収めたのは、最も多く牛乳や乳製品を摂取している被験者達で、また、乳製品を多く摂取する人は、そうでない人に比べて、全体的に健康が維持できているとの結果も出ているという。
■魚や野菜、果物豊富な食生活がADHDを改善する可能性 米研究 ― 2012年02月08日
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2850305/8286294
AFP BB News > ライフ・カルチャー >ヘルス 2012/01/14
AFP BB News > ライフ・カルチャー >ヘルス 2012/01/14
米シカゴ(Chicago)のノースウエスタン大学医学部(Northwestern University Medical School)のチームは、注意欠陥・多動性障害(ADHD)の改善方法を探るため、添加物や着色料を抜き糖分を控え目にした食事を摂るファインゴールドダイエットやメガビタミン療法、オメガ3脂肪酸サプリメント療法などの研究に加え、「西洋型」の高脂肪・低繊維食とADHDの関連性を示したこれまでの研究を総合的に評価した結果を、1月9日の米小児科専門誌「ピディアトリクス(Pediatrics)」に発表したところに依れば、親が子供に魚や野菜や果物、豆、全粒粉が豊富に含まれたヘルシーな食事を与えるよう心掛けるだけで、症状改善に役立つ可能性があるという。但し、対象とした研究の一部に矛盾する証拠が示されていることからも、食事療法は代替あるいは二次的なアプローチとして考えるべきだという。過剰行動、不注意、衝動的行動を特徴とするADHDの原因は、遺伝要因や社会的・環境的な影響が指摘されてきたが、詳しいことは分かっていない。糖分と脂肪分の多い食事を摂ると症状が悪化するとした研究もある。
治療において、向精神薬「リタリン」が処方されることが多く、鉄分のサプリメントの摂取や、食事から添加物や着色料を抜く食事療法が大人気だが、評価の結果、科学的根拠はほとんどないことが分かった。同様に、小麦、卵、チョコレート、チーズ、ナッツなど、アレルギーの原因となりうる食物を抜いた食事に関しても、効果は限定的で、効果の程度もプラシーボ(偽薬)並だった。メガビタミン療法に至っては、効果が認められないばかりか、長期的には危険でさえある可能性が浮上した。尚、亜鉛と鉄欠乏性貧血との関連性については、さらなる調査が必要だという。
親が子供の過剰行動の原因と考える二大要素の糖分とダイエット炭酸飲料についても、ADHDとの関連性は証明できていない。
■脳卒中や心臓病、10年後の確率は? ウェブで簡単予測 ― 2012年01月27日
大阪府立健康科学センターが、1995~2000年に大阪府、秋田県、茨城県、高知県の8,886人に実施した健康診断のデータを基にして、10年後に脳卒中や心臓病などになる確率を予測式をウェブサイト(http://www.kenkoukagaku.net/yosoku/)に公開した。
対象者は40~75歳で、性別、年齢、身長、体重、血圧、中性脂肪やコレステロール値、喫煙や飲酒習慣の有無など計12項目を入力すると、1年後・5年後・10年後の発症確率と、平均と比べたリスクが表示されるので、発症確率を下げるために、ダイエットや禁煙・禁酒・高血圧の改善など具体的にどんなことをすれば、どれだけ改善効果があるかも示される。
■生姜と同程度の冷え抑制効果が「ココア」にも ― 2012年01月22日
森永製菓が「ココア」の冷え性を抑制する効果を「ショウガ」と比較検証した試験の結果を公表した。ココアとショウガは、その冷え性抑制効果の現れ方に違いはあるものの、冷え性を抑制する食品であることが分かったという。
この試験は、冷え性と判断された健常成人11名(女性)が、約70度で100mlの純ココア+牛乳とショウガ+牛乳を飲料摂取後に、医療用サーモグラフィーにて手の甲表面を5分間隔、首表面 / 額表面 / 頬表面 / 鼻表面の温度変化を10分間隔で測定したもので、その結果、手の甲と鼻の体表面温度については、ショウガの方が飲料摂取後の温度上昇の立ち上がりが速く、温度上昇も大きい傾向を確認。しかし、その後ショウガは急速に温度低下が始まるのに対し、ココアは温度低下が緩やかで、ショウガより約0.5度高い表面温度が維持することが確認された。更に、首 / 額 / 頬の体表面温度は飲料摂取による温度変化は小さいが、温度上昇はココアの方が僅かに大きく、温度低下もココアの方が緩やかであった。
▼森永製菓 > What's New > カカオ栄養研究所 冷え性改善効果(ショウガとココアの比較)を更新!(2012/1/11)
■赤外線での癌治療法開発 マウス8割完治、副作用なし ― 2011年12月02日
米国立保健研究所(NIH)の小林久隆チーフサイエンティストらが、11月6日付の米医学誌ネイチャー・メディシン(電子版)に発表したところによれば、体に無害な赤外線を使った新しい癌治療法を開発し、マウスの実験では8割で完治、副作用もなかったという。
光を受けると熱を出す特殊な化学物質と、癌細胞のたんぱく質(抗原)に結びつく抗体を結合させた薬を作り、この薬を注射して、翌日、がん細胞の表面に付いたところで、近赤外線を当て、発熱させて癌細胞を破壊する治療法で、近赤外線は無害で、熱を出す化学物質も体の中で代謝されるため「安全性は高い」という。
実験は、2週間で死んでしまう悪性癌のマウスに、この薬を注射し翌日に近赤外線を1日15分照射する治療を2日間実施。これを1週間おきに4回繰り返し、8割で癌が完治したという。
■軽度の前立腺肥大症状への対処法 ― 2011年11月13日
http://health.nikkei.co.jp/hsn/article.aspx?id=MMHEb1000012092011&list=3
NikkeiNet いきいき健康 海外ニュース 2011/09/12
NikkeiNet いきいき健康 海外ニュース 2011/09/12
男性では、加齢に伴い前立腺肥大症の発症が一般的となる。米国立医学図書館(NLM)は、軽度の前立腺肥大症状への対処法として下記のようなものを勧めている:
- 尿意が発生したらすぐに排尿する。
- 特に夕食後には、カフェインやアルコールの摂取を制限する。
- 就寝前2時間の水分摂取量を制限し、水分は終日にわたって摂取するようにする。
- 症状を悪化させる可能性があるため、抗ヒスタミン成分やうっ血除去成分を含有する市販薬(OTC)は、避ける。
- 定期的に運動をし、体を温める。
- 可能な限りストレスを抑制する。
▼原文:Health Tip: Caring For an Enlarged Prostate
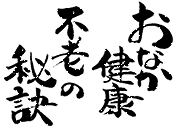



最近のコメント