・[探健くらぶ]平均寿命より長生き! ― 2006年09月17日
2006/09/17
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060919ik02.htm
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/17
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/17
東京都老人総合研究所でアンチエイジングの研究をする白沢卓二さん(48)によれば、日本人の平均寿命は男性が78歳、女性が85歳だが、「まだ、延びる」と見る。 「以前は100歳以上の人から、長寿遺伝子を探したこともあったが、多くの人が長寿を迎えていることから、遺伝的な要因よりも生活習慣や環境が重要」という。
長寿につながる生活習慣とは、バランスの良い食事で栄養を取り、運動で筋力を維持、育て、前向きな気持ちで日々を過ごす――ことという。
男性は社会的なストレスで寿命に影響されやすいとされ、社会変化が著しいロシアでは男性寿命が女性より13歳も短い。日本でも男女差は7歳で、50年前の4歳から少しずつ開いてきている日本は男性にとってやや厳しい国になっているのかもしれないと結んでいる。
・慢性閉塞性肺疾患:ビタミンC不足、老化が発症の危険性高める ― 2006年09月18日
2006/09/18
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/09/20060918ddm013100003000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/09/18
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/09/18
喫煙が主因とされる肺の病気「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」は、気管支の粘膜がただれて気道が狭くなったり、肺の組織が壊れて、肺への空気の出入りが悪くなる病気で、初期は運動時に息切れがあり、悪化すると呼吸困難を起こして死に至ることもある。
この「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」は、ビタミンCの不足や老化によって発症の危険性が高まることを、東京都老人研究所などがマウスを使った実験で突き止めた。
研究チームによれば、ビタミンCには老化を抑制する作用があり、遺伝子操作したマウスは、ビタミンC不足で老化が進み、そこにたばこの害が重なってCOPDになったと考えられるという。
・お茶の「テアニン」が重症の月経前症候群を緩和 ― 2006年09月19日
2006/09/19
サプリ1日量の5倍摂取で、太陽化学が確認
太陽化学(三重県四日市市)と共同研究を行った三重県立看護大学スタッフが、8月25日開催の第32回日本看護研究学会学術集会で発表したところによれば、月経前症候群(PMS)重い女性が、緑茶や紅茶に多く含まれるアミノ酸のテアニンを従来の摂取目安量の5倍量となる1g/日をとったところ、症状が緩和することを確認したという。但し、被験者全員について調べると、精神的症状ではテアニンの摂取によりPMS症状の緩和効果が認められたが、身体的および社会的症状を合わせた総合評価では、改善の傾向が見られるものの、はっきりとした差にはならなかったという。
太陽化学はテアニンを食品添加物として「サンテアニン」の商品名で1994年から販売している。
・急性脳症:スギヒラタケ、筋肉壊す毒で腎不全悪化? ― 2006年09月19日
・中国で40歳以上の死因、癌や脳血管疾患、心臓病が筆頭に ― 2006年09月21日
2006/09/21
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200509/399029.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/09/21
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/09/21
米 Tulane大学のJiang He氏らが、New England Journal of Medicine(NEJM)誌2005年9月15日号に発表した研究によれば、中国に住む40歳以上16万9871人について、1991年から約10年間追跡、延べ123万9191人・年の追跡調査を行い、20,033人の死亡を記録した結果より、中国における近年の40歳以上の死因は、癌や脳血管疾患、心臓病が上位を占め、発展途上国の死因として多い感染症などをしのぐことが明らかになったという。これは、経済の発展に伴い、居住環境や栄養状態、医療サービスなどが改善されたこと、また、脂肪分摂取量の増加や、運動不足などが原因として考えられる。
▽論文のアブストラクト:「Major Causes of Death among Men and Women in China」
・ワカメが脂肪を燃焼し肥満を防ぐ ― 2006年09月21日
2006/09/21
北海道大学大学院水産科学研究院教授の宮下和夫氏らが、サンフランシスコで開かれた米国化学会(ACS)年次集会で発表したところによれば、ワカメに含まれる褐色の色素フコキサンチンにより、マウスの腹部脂肪が縮小し、体重が5~10%減少することを突き止めた。また、フコキサンチンには、オメガ-3脂肪酸であるDHAの産生を促す働きがあることもわかったという。
DHAは、アテローム性動脈硬化症の一因となる悪玉コレステロール(LDL)を減少させる。
・内臓脂肪 高所で分解!? ― 2006年09月24日
2006/09/24
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060924ik01.htm
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/24
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/24
日本山岳会理事で、鶴見大歯科麻酔科助教授の野口いづみさんによると、実際に、登山と健康の関係が注目を集めており、研究成果も出始めたとのこと。心肺機能が高まり、森林浴の効果で心身のストレス軽減につながるという。低酸素状態の高所では、エネルギー消費が増大し、内臓脂肪が分解される可能性が示されているという。▼登山でのバテ無い歩き方:
- 二本のレール上を歩くような感じで
- 歩幅小さく
- 足音を立てない
- 靴の裏を見せない
- 呼吸はゆっくり吐く、パクパクしない
・がん「最初にたんぱく質損傷」発症メカニズムで新説 ― 2006年09月25日
2006/09/25
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060925ik03.htm
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/25
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/25
がんは、遺伝子の変異が積み重なって起きるとされているが、それ以前に、たんぱく質が損傷することで、細胞が「がん」特有の性質を持つとする新説を、渡辺正己・京都大学原子炉実験所教授らが、 28日の日本癌学会で発表した。
渡辺教授によれば「がんの大半は、染色体に係わるたんぱく質が傷つき、染色体が異常化して細胞分裂が正常に行えない細胞から生まれると考えた方が矛盾がない」という。
たんぱく質の損傷は、活性酸素・紫外線・放射線など様々な要因で細胞内にできる有害物質「ラジカル」による。
・母乳やヨーグルト、大腸ポリープ抑制効果 ― 2006年09月26日
2006/09/26
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060926ik04.htm
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/26
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/09/26
今回の日本癌学会に、国立がんセンターがん予防・検診研究センターの神津隆弘室長らが発表したところによれば、ヨーグルトなどに含まれるたんぱく質「ラクトフェリン」は、人間の母乳、特に初乳に多く含まれるが、この「ラクトフェリン」に、大腸ポリープ(腺腫)を縮小させる効果があるという。
・アトピーのかゆみを軽くする新規オリゴ糖の効果、王子製紙が発見 ― 2006年09月27日
2006/09/27
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200509/400054.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/09/27
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/09/27
樹木成分由来のキシロオリゴ糖の開発を進めている王子製紙は、京都府立大学との共同研究で、薬剤によってアトピー様皮膚炎を発症するNC/NgaマウスにUX10を経口投与したところ、皮膚症状を軽減したこと、及び兵庫県加西市の北条動物病院との共同研究で、難治性のアトピー性皮膚炎を発症している犬に対する投与で、皮膚炎とかゆみが軽減したほか、ダニなどに対するIgE値が低減したことより、新規オリゴ糖UX10に、アレルギー症状の改善作用を見出したと発表した。▽王子製紙のプレスリリース:「2005/09/27 新規オリゴ糖のアレルギー改善作用を発見」
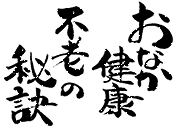



最近のコメント