■「100%乳酸菌食品」で、善玉菌優勢の腸環境へ! ― 2009年06月03日
■■
■■ 100%乳酸菌食品━━━━━善玉菌優勢な腸内環境へ!
■
■ 若さを保ち、健康維持を目指す第一歩は、
■ 「善玉菌優勢」の腸内環境への改善!
■ 善玉菌の代表である乳酸菌を、毎日補給することをお勧めします。
■
■ 活きた乳酸菌100%成分の健康食品「ニブロン」。
┃ その質と量でプロバイオティクスを実感して下さい。
┃
┃ カプセルタイプになって、飲み易くなってます。
┃ 購入は、ここ!-------->> 「 Ohji Inter Health 」
┃
┃
┃ 安全、安心の
■ (財)日本健康・栄養食品協会許可の JHFAマーク許可健康食品
■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
------------------------------PR-□
◎鎌倉山の薔薇 ― 2009年06月03日
◎私的・至宝の彩り ― 2009年06月04日
■突発性難聴になってしまいました ― 2009年06月12日
(この記事の訂正版を2009/07/20「「メニエール病」について」にて行いました。)健康について、情報を発信し、健康に気をつけていたつもりの本人が、今回情けなくも突発性難聴を再発いたしました。
反省の意味を込めて、突発性難聴についての、情報を探ってみました。 その中でも、自分に施された治療とその後の経過等の体験を通しての判断を交えて、『ウィキペディア(Wikipedia)』の情報がお勧めです。
若しも不幸にも、片方の耳が聞こえなくなってきたような症状を発症した場合は、自己判断をせずに、『ウィキペディア(Wikipedia)』上の、原因・症状を参考にされて、一刻も早く大きな病院に駆け込んで治療を受けてください。
▼『ウィキペディア(Wikipedia)』上の、原因・症状:
原因 :
内耳などに障害が生じる感音性難聴の一種と考えられているが、現在のところ原因は不明である。
症状 :
毛細血管の血流が妨げられ内耳に血液が十分届かずに機能不全を引き起こすという内耳循環障害説、ステロイド(感染症に対して抗炎症作用を持つ)が効果を発揮することからウィルス感染を原因とする説などがある。 患者調査の傾向からストレスを原因の一つとする意見もある。耳以外の神経症状(四肢の麻痺など)は見られない。遺伝の要素は見つかっていない。分野としてはあまり研究が進んでいないのが現状である。軽~重度の難聴(低音型・水平型・高音型など)と耳鳴りなどが中心であり、それに加えて音が「異常に響く」「割れる」「二重に聞こえる」「音程が狂う」など、その副症状も人によって様々である。めまいや吐き気を訴える事もある(この場合はメニエール病も疑われる)。ほとんどの場合片側のみに発症するが、稀に両側性となる場合もある。
治療:誤解されがちな点であるが、突然の失聴が患者に与える精神的負担は極めて大きい。外見的に障害が見られず周囲の理解が得られにくい事に加え、健康体からの突然の発症からくるショックや、耳の異常を常時自覚せざるを得ないため、深刻なストレスと精神的苦痛を常に強いられる。特に大人になってからの中途失聴は障害認識が難しく、それまで言語コミュニケーションにより築いてきた友人関係・家族関係・社会的地位などを危うくする場合もある。
適切な早期治療と安静が極めて重要である。症状を自覚した場合は速やかに設備の整った病院(大学病院など)で耳鼻咽喉科の専門医の診断を受けることが肝要。判断と治療の困難さから小病院・一般医では知識や設備が不足している場合が多く、誤診による手遅れ・認識間違い等に注意が必要である(実際に聴力低下が見られても、ある程度会話が聞き取れれば正常とみなされ異常と診断されないこともある)。
なお治療方法は前述の仮説を想定したものが中心となる。一般的には発症から約2週間以内が治療開始限度と言われており、これを過ぎると治癒の確率は大幅に低下する。治療開始が早いほど、その後の症状に大きな差異が出るとの考えもある。重度であれば入院での加療が望ましい。
* ウイルス性内耳障害改善を目的とする、ステロイド剤投与(比較的効果が高い)。
* 内耳循環障害改善を目的とする、血流改善剤(アデホスコーワ等)、代謝促進剤(メチコバール等)、高気圧酸素療法、星状神経節ブロック注射等。
* 内リンパ水腫改善を目的とする、利尿剤(イソバイド、メニレット等)投与。
◎ 池の蓮 ― 2009年06月13日
◎私的・至宝の如き一輪 ― 2009年06月13日
■がん~ 世界の専門医が推奨する予防10カ条 ― 2009年06月22日
健康増進クリニック院長の水上治(みずかみ・おさむ)氏 へのインタビュー記事▼がんに関する論文や文献が満載
米国の「世界がん研究基金」から2007年11月に出版された、がんに関する4400の文献論文集「食べもの、栄養、運動とがん予防」は、世界の権威者の論文が掲載されている素晴らしい本で、膨大なデータが収められており、非常に科学的だ。この文献はネットで閲覧することもできる。
Food,Nutrition,Physical Activity,and the Prevention of Cancer
http://www.dietandcancerreport.org/上記の文献論文集「食べもの、栄養、運動とがん予防」の中で提言されている「がん予防10か条」の中には、もはや喫煙は含まれていない。喫煙はあらゆるがんの発生率を高めることはもはや常識であり、あえて10か条に明示するまでもないという考えのようだ。
▼がんは、酸素を嫌う
・第1条:「肥満」について。
肥満指数BMIの数値を21~23にすること。これが30以上になるとがん発生リスクは5割増しにもなるという。「がん細胞は、ブドウ糖を大量に消費し、脂肪はプロモーターとなるので、肥満という栄養過多の環境は、がん細胞が増えやすい環境なのだ」但し、痩せすぎも免疫低下を招く。
・第2条:「運動」について。
ウォーキングなど軽度の運動を毎日30分ほど実践することを提唱している。その後、60分程度のジョギングや水泳、テニスなどのやや激しいものへと移行することを推奨している。特に乳がんと大腸がんに関しては運動の重要性が高く、ほとんど運動しない人に比較してリスクが半分になるという。
▼肉は、300g/週 以下に制限がん細胞は酸素を嫌う嫌気性の細胞だから、血流が良くて酸素が多いほど発症が抑制されます。軽度の運動は免疫力を高める。たばこがよくない理由のひとつは、酸素供給を阻害する点にある。
・第3条:「高エネルギーの飲食物」について。
砂糖入り飲料や脂肪などの高エネルギーの食べ物の摂取を制限している。和食主体の食事が望ましい。
・第4条:「植物性食品」について。
600g/日の野菜と果物を摂取することを促している。また穀類に関しては、できるだけ精白されていないものを推奨している。 「精白すると表皮部分に含まれているビタミンやミネラル、そして食物繊維が激減する。五分づき米にするとか、五穀米にするなど工夫が必要で、できるだけ食物繊維を摂ることを意識しよう」
・第5条:「動物性食品」について。
赤肉(牛・豚・羊)を制限し、加工肉(ハム、ベーコン、サラミ、燻製肉、熟成肉、塩蔵肉)を避けることを促している。具体的には、赤肉は300g/週以下が目標。 「肉食が多いと、腸内環境が悪化し、悪玉菌が増えやすくなります。300g/週以下というのは、ステーキならば週に1 回が上限だし、毎日の献立に肉が入る場合は、ほんの少しの量にすべき。和食主体の献立であればクリアする筈」
できるだけ理想的な生活習慣に近づけることを心がけたい。毎日運動をし、和食主体の食事を心がけていれば、自ずと理想的な環境を作ることができる。
◎競い合う池の華 ― 2009年06月22日
◎日本の夏? ― 2009年06月22日
■がんから身を守る10か条~その2~ ― 2009年06月24日
健康増進クリニック院長の水上治(みずかみ・おさむ)氏 へのインタビュー記事(その2)▼酒は百薬の長
・第6条:「アルコール」。
男性は、2合/日程度まで。ビールなら350mlを1本~2本/日。女性は男性の半分の1合/日程度。二日酔いをするような過度の飲酒は、免疫力を下げ、風邪も引き易くする。1合/日 程度の飲酒は、逆に免疫力を高めることが知られており、飲酒量とがん発症のリスクとの関係はU字カーブを描いている。全く飲まないケースよりも1合程度を飲む人の方がリスクが低い。ほろ酔い加減になる位の飲酒は、血流を良くしリラックス効果があり「酒は百薬の長」という諺にも表れている。
・第7条:「保存・調理」について。1日の食塩摂取量を6g/日までとし、できれば5gを目標数値として挙げている。さらにカビの生えた穀物や豆類を避けるよう促している。日本人はおおよそ11g/日 摂取しているので、この数値はかなり厳しい。
▼がんの再発予防のためには生活改善が重要
毎日味噌汁を1日に2~3杯飲んでいる人は、胃がんと乳がんの発症が半分になったというデータもあり、大豆に含まれるイソフラボンががん予防作用を持つという、日本人の食生活を考慮する必要もある。米国「世界がん研究基金」が2007年11月に出版した「食べもの、栄養、運動とがん予防」に謳われた「がん予防10か条」は、欧米人を主対象としているので、食生活が違う日本人には異なる部分もあると考えた方がよいだろう。
・第8条:「サプリメント」。
あくまでも通常の食事があって、その不足分を補うものとしてサプリメントがあることを認識しなければならない。食事をおろそかにしてサプリメントで健康を得ようというのは間違い。野菜を沢山食べてがん発症リスクを低くしたというデータはあるが、サプリで抑制できたというデータは極めて少ない。
・第9条:「母乳哺育」について。
6カ月間は、母乳哺育をすることを勧めている。これは母親を主に乳がんから、子供を肥満や病気から守るために有効だからだ。
・第10条:「がん治療後」について。がん治療した後、食事や栄養、体重、運動について専門家の指導を受けることを勧めている。再発を防ぐために、9条までに提唱されてきたような生活習慣の改善が再発予防に有効だという。
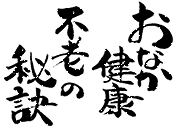









最近のコメント