■京大など、脂肪酸受容体「GPR43」が肥満を防ぐ機能を有することを解明 ― 2013年06月10日
京大 薬学研究科の木村郁夫助教、同・大学院生の井上大輔氏、奈良県立医科大の小澤健太郎准教授、金沢大の井上啓教授、滋賀医科大の今村武史准教授らの研究チームが、英科学誌「Nature Communications」5月7日の電子版に発表したところに依れば、腸内細菌が産生する栄養(酢酸などの短鎖脂肪酸)を認識する脂肪酸受容体「GPR43」が脂肪の蓄積を抑制し、肥満を防ぐ機能を有することを明らかにしたと発表した。
食事(食餌)によるエネルギーの摂取は、生命にとって非常に重要で、ヒトの身体は必要以上のエネルギーを摂取できた場合は、後にエネルギー不足になった際の非常用エネルギー源とするために脂肪として体内に蓄えられる仕組みを持つが、先進諸国では過度な食事による過剰なエネルギー摂取の結果として脂肪を必要以上に膨大させ、肥満更には糖尿病に代表される生活習慣病などの代謝疾患が大きな問題となっている。
近年、腸内細菌がその宿主のエネルギー調節や栄養の摂取などのエネルギー恒常性維持に深く関与し、肥満や糖尿病などの病態に影響することが明らかになり、食事と腸内細菌、エネルギー恒常性への関係が注目されるようになっている。
腸内細菌によって産生される酢酸に代表される「短鎖脂肪酸」は、主に宿主のエネルギー源として利用される。研究チームは2011年に、この「短鎖脂肪酸」がエネルギー源としてのみではなく、体内のエネルギー状態の指標となり、脂肪酸受容体「GPR41」を活性化することにより交感神経系を介して、エネルギー恒常性の維持に関わることを明らかにした。
今回の研究では、この「短鎖脂肪酸」のもう1つの受容体である「GPR43」の脂肪組織における機能と、腸内細菌による「GPR43」を介した宿主へのエネルギー恒常性維持への関与について、マウスを使った実験にて次の事が明らかになった。
1.食事時、食物より直接得られるブドウ糖や脂肪酸などのエネルギー源と同時に、腸内細菌によって「短鎖脂肪酸」がエネルギー源として産生されること。
2.通常は、この短鎖脂肪酸はエネルギー源としてだけ使用されるが、過度な食事により過剰エネルギーが得られた時に、同様に「短鎖脂肪酸」も過剰に上昇すること。
3.この過剰に上昇した「短鎖脂肪酸」を認識するセンサ受容体「GPR43」が活性化し、脂肪組織への過剰エネルギー蓄積を抑制し、エネルギー消費の方向へ誘導し、結果として過度な肥満から起こる代謝機能異常を防ぎ、また体全体のエネルギー消費を高め、体内のエネルギー恒常性の維持に働くということ。
以上から、腸内細菌叢による宿主の恒常性維持に働く、全く新たなエネルギー調節機構が明らかとなり、この短鎖脂肪酸受容体GPR43を標的とした肥満や糖尿病に代表される生活習慣病に対する予防・治療薬への応用が可能となるかもしれない。
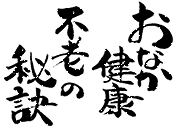



最近のコメント