■乳酸菌LGG菌の効果 アトピー、ぜんそく、花粉症…症状軽減に期待 ― 2008年03月01日
毎日新聞 ライフスタイル > 健康 > アーカイブ 2008/02/23
ヨーグルトに含まれる乳酸菌の一つ、LGG菌が花粉症やアトピー性皮膚炎等のアレルギー症状の軽減に効くという話題についての記事。最近使われるようになった、「プロバイオティクス」という言葉で、生きたまま腸に届いて健康に良い働きをする微生物のことで、一部の乳酸菌もプロバイオティクスだ。
フィンランド、ツルク大学のセポ・サルミネン教授(食品化学)、エリカ・イソラウリ教授(小児科)らが、01年春にイギリスの医学雑誌「ランセット」に、乳酸菌LGG菌がアトピー性皮膚炎に効果がある可能性を示す研究報告を発表した。サルミネン教授らは、アトピー性皮膚炎の症状のある妊産婦132人に、出産予定日2~4週間前から出産後半年間にわたってLGG菌と偽薬を投与した。その結果、生まれてきた子どものアトピー性皮膚炎の発症率は、LGG菌を取った妊産婦の方が偽薬と比較し約半分と低くかった。
4歳の時点でも、LGG菌を投与した群ではアトピー性皮膚炎の発症頻度が低く、7歳時点で投与したLGG菌によるアトピー性皮膚炎発症の総合リスクの低減も継続的に観察された。
アトピー性皮膚炎に対するLGG菌の予防効果のメカニズムは、完全には解明されていないが、LGG菌によって腸内のバリアー機能が強くなり、アレルギーの原因となるアレルゲンが体内に吸収され難くくなるとためと推測される。乳酸菌のLGG菌は、1985年、アメリカのタフツ大のゴルディン教授、ゴルバッハ教授が人の腸内から発見し、フィンランドの会社が事業化し、世界40カ国以上でヨーグルトや乳酸菌飲料として商品化されている。
その特徴は、胃酸や胆汁酸に強いため、 生きたまま腸に届き、腸管への粘着性が高く、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らす--などが挙げられる。
最近の研究では、母親の腸内細菌が子どもの腸内細菌に大きな影響を与えることも明らかにされ、妊娠した母親の腸内環境が良好だと、子どもがアレルギー体質を受け継がない可能性が高くなるという。普段の食生活で大切なのは、LGG菌を継続して取ること。 フィンランドではジュースのほかに、チーズや牛乳の中にもLGG菌を入れているという。 特に風邪などをひいて抗生物質を投与された時や、環境が大きく変わる海外旅行時などは積極的に取ることが必要だ。
■100%乳酸菌・ニブロンって何なの? ― 2008年03月01日
■加工食品のアレルギー表示、エビとカニも追加へ 厚労省 ― 2008年03月02日
加工食品の食物アレルギー表示について、厚生労働省は、小麦、そば、卵、乳、落花生の5品目ある表示義務の対象に、エビとカニを追加する方針を決めた。厚労省研究班(班長=海老沢元宏・国立病院機構相模原病院)が05年度、アレルギー患者約2300人を調べたところ、呼吸困難などショック症状が重かった食物は、義務対象の5品目(小麦、そば、卵、乳、落花生)に次ぐ6位がエビ、13位がカニと高かく、大豆やゼラチン、イカなどと同様に、メーカーに表示を促す「推奨」対象の20品目に含まれていた。
■毒ギョーザの影響大 「食品に対して不安ある」9割超 ― 2008年03月04日
Yahoo!ニュース > 経済 > MONEYzine 2008/02/27
ネットリサーチのマイボイスコムが、『食の安全』に関する調査を2008年2月1日~5日に実施し、15,256件の回答を集め、食品への不安や表示項目への信頼度などについて聞いた結果は、調査結果における、食品の安全性に対して、
「不安を感じている」 53%、
「やや不安を感じている」 40%、
合計で93%もの人が不安を感じている。その不安対象項目は、
「残留農薬」が 88%、 「添加物」が 64%、 「環境汚染物質」が 53%、 「食中毒菌」が 49% だった。▼ MoneyZineの記事には、もっと詳しいアンケート結果が掲載されています。
https://moneyzine.jp/rd/ht/aid/33664▼マイボイスコムの、[11506] 食の安全(第3回) には、上記のアンケート結果が掲載されています。
http://www.myvoice.co.jp/biz/surveys/11506/index.html
■善玉のHDLコレステロール値を上げたいのですが? ― 2008年03月09日
毎日新聞 ライフスタイル > 健康 > アーカイブ 2008/03/07
◇HDLコレステロール値を上げるための基本は運動、たばこも止めて血液中のコレステロールには、悪玉のLDLコレステロールと善玉のHDLコレステロールがあり、悪玉コレステロールが血管内に蓄積すると、動脈硬化になり、心筋梗塞などのリスクが高くなる。HDLは悪玉コレステロールを掃除する働きをする。
吉田雅幸・東京医科歯科大生命倫理研究センター教授(脂質異常症・老年病内科)によれば、LDLを低くしても、HDLが低いままだと動脈硬化は進むので、HDLを引き上げることも動脈硬化の防止につながる。
LDLコレステロールとHDLコレステロール値の比が重要。この比が高いほど心筋梗塞がより進むことが、海外の大規模調査で判明しているという。
LDL/HDL=2.5以上だと動脈硬化が進みやすく要注意で、2以下を脂質改善の目安としたい。糖尿病や高血圧の人は、2以下でも動脈硬化が進むとの報告があり、1.5以下を目標にすべきだという。HDLコレステロール値を上げるための基本は、運動すること。禁煙も上げる要因になる。
■趣味の写真/早春の松田山からの富士 ― 2008年03月12日
神奈川県足柄上郡松田町・松田山からのスナップです。湯河原梅林を訪れた帰路に松田山に立ち寄りましたが、すごい人手に圧倒されましたが、やっとの思いで人手のいない近接する菜の花山から、杉の木を避けて富士を収めました。
|
Olympusのコミュニティーサイト「FotoPus」(http://fotopus.com/index.html)や、「Photohito」というサイトに、 ニックネーム「トシ坊」で投稿してますので、下記のスナップ一覧から、お気に入りのスナップをクリックして、投票していただければ幸いです。 主なスナップの一覧は、こちら! と、http://photohito.com/user/1097/ |
■BMI上昇は男性の食道腺癌、甲状腺癌のリスクを高める ― 2008年03月15日
Nikkei Medical Online HOT NEWS 2008/03/07
女性の子宮内膜癌、胆嚢癌などもリスク上昇英国Manchester大学のAndrew G Renehan氏らが、Lancet誌2008年2月16日号に発表したところによれば、個々の癌とBMIの関係の強さを調べた大規模な系統的レビューとメタ分析の結果、BMIが5kg/m2増加するとリスクが1.5倍程度になる癌が複数あることが示された。そこには性別、人種による差も認められた。
BMI上昇との関係が男性でより強力だったのは、結腸癌(リスク比は1.24と1.08、P<0.0001)と直腸癌(1.08と1.01、P=0.003)。女性の方が強力だったのは腎臓癌(1.18と1.35、P=0.004)。
≪男性≫
1.BMIが5kg/m2増加当たりのリスク比が強力かつ有意に上昇していたのは、
食道腺癌(リスク比1.52、P< 0.0001)、甲状腺癌(1.33、P=0.02)、結腸癌(1.24、P<0.0001)、腎臓癌(1.24、P<0.0001)。
2.弱いが有意なリスク上昇が見られたのは、
メラノーマ(1.17、P=0.004)、多発性骨髄腫(1.11、P<0.0001)、直腸癌(1.09、P<0.0001)、白血病(1.08、P=0.009)、非ホジキンリンパ腫(1.06、P<0.0001)。
3.研究間の均質性が低かったのは、甲状腺癌と肝臓癌に関する研究だった。≪女性≫
1.BMIが5kg/m2増加当たりのリスク比が強力に上昇していたのは、
子宮内膜癌(1.59、P<0.0001)、胆嚢癌(1.59、P=0.04)、食道腺癌(1.51、P<0.0001)、腎臓癌(1.34、P<0.0001)
2.弱いが有意なリスク上昇が見られたのは、
白血病(1.17、P=0.01)、甲状腺癌(1.14、P=0.0001)、閉経後の乳癌(1.12、P<0.0001)、膵臓癌(1.12、P=0.01)、結腸癌(1.09、 P<0.0001)、非ホジキンリンパ腫(1.07、P=0.05)。
3.均質性が低かったのは
子宮内膜癌と肺癌、白血病に関する研究だった。≪喫煙≫
肺癌では、喫煙が強力な交絡因子で、喫煙者のBMIは非喫煙者より低い傾向があった。≪人種≫
人種との関係も評価され、有意な地域差が認められたのは、閉経前と閉経後の乳癌。
閉経前の乳癌のリスク比は、北米では0.91(0.85-0.98)、欧州と豪州では0.89 (0.84-0.94)、アジア太平洋地域1.31(1.15-1.48)(P=0.009)、
閉経後の乳癌は、北米では1.15(1.08-1.23)、欧州と豪州では 1.09(1.04-1.14)、アジア太平洋地域で1.31(1.15-1.48)(P=0.06)と、
いずれもアジア太平洋地域の集団でリスクが高かった。
■写真投稿サイトのご紹介 ― 2008年03月16日
「Photohito」というサイトに、ニックネーム「トシ坊」にて投稿しています。
画像サイズが、大きいので綺麗にご覧いただけます。 是非、アクセスして、ご批評コメントをアップいただれば幸いです。カメラメーカー、カメラ、カテゴリー別に多数の方が投稿していますので、非常に面白いですよ。
■“睡眠不足は肥満のもと”5時間未満だと1.4倍に ― 2008年03月19日
日本大学の兼板佳孝講師(公衆衛生学)らが12日に発表した、地方公務員21,693人に1999年と2006年に睡眠時間などを尋ね、両時点での健康診断データと比較した大規模調査の結果によれば、睡眠時間が短いと肥満や糖尿病などの生活習慣病になり易いという。睡眠時間が5時間未満の場合、5時間以上に比べて肥満の人が約1.4倍であることがわかった。逆に、99年で肥満の人は06年に睡眠時間が短くなっている傾向があり、肥満と短時間睡眠が悪循環の関係になっていることがうかがわれた。
また、高血糖には、睡眠時間が5時間未満の方が約1.3倍なり易く、睡眠時間が99年時点では5時間以上だったのに、06年時点で5時間未満に減少した人は、中性脂肪の数値が高い状態に約1.4倍なり易いことがわかった。
■コーヒー飲む人は糖尿病になりにくい? 九大が調査に ― 2008年03月22日
糖尿病になり難くくなるとされるコーヒーの「効能」が本物かどうか、九大医学部の古野純典(この・すみのり)教授(予防医学)らの研究グループが近く調査に乗り出す。糖尿病予備軍のちょっとメタボな人に5杯/日のコーヒーを約4カ月間飲み続けてもらい、血液中の血糖値の変化を調べる。条件に当てはまる調査参加者を募っている。過去の研究は、実際にコーヒーを飲んで効果を調べる期間が最長1カ月ほどで信頼性に欠けるため、コーヒーメーカーの協力を得て本格的な検証をするもので、参加者60人を3グループに分けて実施し、それぞれ「カフェイン入りコーヒー」「カフェイン抜きコーヒー」「水」を16週間飲み続けてもらう。
問い合わせは、古野教授(平日午前10時~午後5時、 092-642-6114)へ。
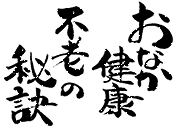



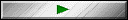


最近のコメント