■母親の腸管内のビフィズス菌は新生児に受け継がれる - ヤクルトが確認 ― 2013年12月13日
ヤクルトは、11月26日に発表したところに依れば、ヨーロッパ研究所、ニュートリシア・リサーチ・ユトレヒト・オランダの研究成果として、出産前の母親の腸管内に常在するビフィズス菌が新生児の腸管に受け継がれることを明らかにしたという。詳細は、米学術誌「PLOS ONE」に掲載された。
ヒトの腸内には1000種超、約100兆個の細菌が棲みつき、複雑な腸内細菌叢(腸内フローラ)が形成されて、ヒトの健康や感染防御に影響を与えていると考えられている。また、胎児は母親の子宮内では無菌状態だが、出産時において産道に定着している細菌との接触あるいは近親者・医療従事者・環境を介して細菌と接触する機会に巡り合い、新生児の腸内細菌叢が形成されていくことが知られている。
この腸内細菌の中でもビフィズス菌は、新生児の腸管内では、出生後の早い段階から多数を占める細菌として知られ、免疫が発達していない新生児の感染防御や乳幼児期の粘膜免疫系の発達において、重要な役割を果たすことが報告されてきたが、新生児に定着しているビフィズス菌の由来についてはよく分かっていなかった。
これまでの研究から、出産前の妊婦及び出生後の新生児の便からビフィズス菌を経時的に単離し、8組の自然分娩母子のうち6組において、母親と同一菌株のビフィズス菌が新生児から検出されることを報告していた。今回の研究では、この成果を踏まえ、複数種類のビフィズス菌株に関して、腸管内に常在しているビフィズス菌をそれぞれ単離し、それらが同一の菌株であることの実証に挑んだほか、分娩様式の異なる母子を対象に、分娩様式による差異についての解析を行った。
具体的には、ベルギー在住の分娩様式の異なる17組の母子(自然分娩:12組、帝王切開:5組)の便からビフィズス菌を経時的に単離し調査した結果、自然分娩で生まれた新生児11名から、母親と同一菌株のビフィズス菌(B. adolescentis、B. bifidum、B. catenulatum、B. longum subsp. longum、B. pseudocatenulatum)が分離され、自然分娩では母親から新生児へ複数のビフィズス菌種が受け継がれることが明らかとなったが、帝王切開で出生した新生児でもビフィズス菌が検出されたが、母親と同一菌株のビフィズス菌は検出されず、腸管内におけるビフィズス菌の定着も自然分娩児と比べると遅いことが確認されたという。
今回の成果を受けて、母親から新生児へビフィズス菌が受け継がれることは、出生後早期にビフィズス菌が優勢な腸内細菌叢が構築され得る要因の1つと考えられ、また母親から受け継がれたビフィズス菌は腸管内において優勢に増殖して、免疫が発達していない新生児を病原菌から守っていると推測される。
新生児の健康の為には、妊婦が良好な腸内環境を維持することが大切だと考えられる。
◎北近江・鶏足寺の紅葉 ― 2013年12月13日
写真仲間に誘われ、鈴鹿から車で一般道を約三時間の琵琶湖東岸
の最北部にある長浜市の鶏足寺へ。そこは緩やかな参道の石段、両側の苔むした石垣、台地の佇まいと共に200本に及ぶモミジの古木の紅葉が見られる北近江随一といわれる紅葉の名所にて、初めての訪問でした。到着は8:30頃。曇り模様で傘を差すほどでは無いが、弱い霧雨にて地面が湿っていて、時折陽が射す絶好の撮影条件でしたが、到着が少し遅かったこともあり人影が多くなってきていました。それほど広いところでは無いのですが、モミジの古木に真っ赤な色が何とも情緒があって、上ばかり見上げてつつ行きつ戻りつしながら長い時間シャッターを切っていました。もう二三日後に訪問すれば、紅い落ち葉の絨毯が参道に敷き詰められている光景に出合えたのかもしれません。それを求めて機会が有れば再訪してみたいと思っています。
(2013.11.22撮影)
Fotopusへの投稿作品の一覧は、こちら! (ここをClickして!)
カメラ :オリンパス OM-D E-M1
レンズ :ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD
撮影場所:滋賀県・長浜市・木之本町・古橋
(2013.11.22撮影)
Fotopusへの投稿作品の一覧は、こちら! (ここをClickして!)
カメラ :オリンパス OM-D E-M1
レンズ :ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD
撮影場所:滋賀県・長浜市・木之本町・古橋
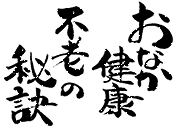




最近のコメント