■フィルターたばこにより肺癌のタイプが様変わり ― 2007年10月07日
米タフツ-ニューイングランドメディカルセンター(Tufts-NEMC、ボストン)のGray M. Strauss博士らが、1975~2003年の米国立癌研究所(NCI)によるSEER(Surveillance Epidemiology and End Results)プログラムのデータを分析した結果を、韓国ソウルで開催された第12回世界肺癌学会で発表したところによれば、1950年代にフィルター付き低タールたばこが導入された時期に一致して、肺癌のうちの腺癌が増え始めたことが判明したという。1950年代には腺癌は肺癌全体の5%にとどまり、扁平上皮癌が最も多かったが、60年代から腺癌が増え始め、75~79年から95~99年までの間に62%増大。女性では75~79年、男性では 80~84年に扁平上皮癌を抜いて最多となった。00~03年には腺癌が肺癌全体の47%を占め、人種、年齢、性別にかかわらず最多と判明。
SEERには喫煙に関する人口統計データがないため、米国の50年間のたばこ生産と消費者の動向に関するデータを検討した結果、フィルター付き低タールたばこの利用と腺癌比率の増大が密接に関連していることが明らかになった。この腺癌の増大は、フィルターを付けたことにより、ニコチン濃度が薄くなるために、喫煙者が発癌物質を気管支や肺の深くまで吸い込むためではないかと推察される。
同学会で発表された別の研究では、手巻きたばこは包装済みのたばこよりも発癌性が高く、肺癌リスクを高めることや、肺癌の家族歴をもつ人は肺癌(特に扁平上皮癌)を発症する比率が高いことなどが示された。
▼原文
:Filtered Cigarettes Blamed for Huge Rise in Type of Lung Cancer
■メタボ対策:まず2.5時間/週の速歩から 内臓脂肪、0.3%/週 減 ― 2007年10月07日
毎日新聞 ライフスタイル > 健康 > アーカイブ 2007/09/28
◇内臓脂肪を確実に減らすには
国立健康・栄養研究所の研究チームは、1966~06年5月に発表された内臓脂肪と運動の関係について報告している論文のうち、内臓脂肪面積をCT(コンピューター断層撮影装置)かMRI(磁気共鳴画像化装置)で測定していることなど、一定の基準を満たした日本など5カ国、計16本の研究結果を分析したところ、内臓脂肪を確実に減らすには、日常生活の中での活動や運動に加え、1週間当たり「速歩(分速90~100m程度)で2.5時間以上」に相当する運動を追加する必要があることを明らかにした。内臓脂肪面積100平方cmの人が、1週間で1平方cm減らすには、毎日1時間程度の速歩相当の運動が必要だという。
各論文の対象者は計582人で、平均年齢は22~67.5歳。肥満度を示すBMIの平均は25.3~35.9。対象者は食生活は変えず、ウオーキングなど一定の時間持続することが可能な運動を週3~7回、8週間~1年続けていた。研究では、身体活動の強度を示す単位「メッツ」を使用。速歩は4メッツで、速歩を2時間続けた時の活動量を「8メッツ・時」と換算した。
2型糖尿病など代謝性疾患の患者を除いた425人分を分析すると、週に約10メッツ・時以上の運動をした場合に、内臓脂肪が減少した。週に10メッツ・時(速歩2時間半相当)の運動をすると、1週間で内臓脂肪が0.342%減少し、活動量に比例して減少の程度も増加。
週に27メッツ・時(速歩毎日1時間程度相当)の運動をすると、内臓脂肪が1%減となった。
■趣味の写真/ 富士/ 日本平から望む富士 ― 2007年10月11日
■趣味の写真/ 富士/ 芦ノ湖を望む富士 ― 2007年10月11日
■趣味の写真/ 富士/ 雲の切れ間に映える富士 ― 2007年10月12日
■富士山の写真集を作りました! ― 2007年10月13日
|
忍野・二十曲峠にて雲が晴れるのを待つこと二時間。 やっと頂上が見え出しました。 その後、山中湖沿いに、帰宅につきました。そのときの、スナップです。 「Photoback」で、写真集を作成してみましたので、左の画をクリックしてみてください。 | ||
|
Olympusのコミュニティーサイト「FotoPus」(http://fotopus.com/index.html)に、 ニックネーム「とし坊」で投稿してますので、下の画像をクリックして、投票いただければ幸いです。
| ||

|

|

|
■飲むと赤ら顔…膵がんリスク1.44倍 ― 2007年10月13日
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2007/10/04
愛知県がんセンター研究所(名古屋市)の調査によれば、酒を飲むと顔が赤くなる人は、そうでない人に比べて、膵臓(すいぞう)がんになるリスクが1.44倍高いことが判ったという。同研究所の松尾恵太郎主任研究員(がん疫学)らが、2001~05年に同センターを訪れた膵臓がん患者138人と、がんではない1373人のアルコールを体内で分解する酵素の遺伝子タイプと飲酒との関係を調べたもの。
■肺がん発見率9割 血液検査で精度3倍 東大医科研 ― 2007年10月13日
横浜市で5日まで開かれていた日本癌学会総会で、東大医科学研究所ヒトゲノム解析センターの醍醐弥太郎・准教授らが発表したところによれば、血液検査で肺がんを高精度で見つける新たな腫瘍)マーカーの組みあわせを開発した。
発見率は約9割で、いま診療で主に使われている3種類に比べて1.5~3倍高く、肺がんの早期発見や術後の治療法選択に役立ちそうだ。同研究グループは、同じ早期に手術をしても、経過に差があることに着目。術後5年以上追跡している約400人の患者の肺がん組織を分析し、特定のたんぱく質三つがいくつ検出されるかで、「5年後の生存率が8割程度」と経過の良い場合から、「生存率2割程度」と悪い場合まで4段階で判別できる方法を開発した。
■早期のピロリ除菌、胃がん予防に効果 ― 2007年10月13日
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2007/10/04
横浜市で開かれている日本癌学会で、和歌山県立医大の一瀬雅夫教授(第2内科)らが、3日発表したところによれば、胃がんを引き起こすとされるヘリコバクター・ピロリ菌の除菌を、胃壁が変化する「萎縮(いしゅく)性胃炎」発症の前にすると胃がんの予防効果が高いという。萎縮性胃炎は、胃壁が薄くなり、胃酸の分泌が減る状態。ピロリ菌感染者の約3割に見つかり、10年以上を経てがんになることが多く、一瀬教授らは、1994年以降に、和歌山県で胃がん検診を受けた40歳以上の男性で、ピロリ菌に感染した人のうち、4129人を約10年間追跡し、胃がんの発症率などを調べたもの。
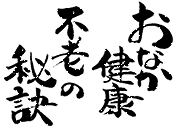






最近のコメント